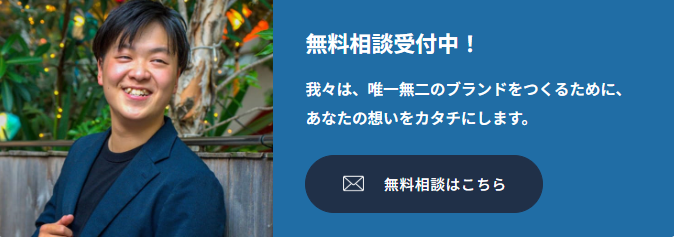評価制度とは?作り方や種類、導入目的を徹底解説!
企業が成長し、競争力を維持するためには、従業員の能力や成果を正確に評価し、それを活用することが欠かせません。その中心的な役割を果たすのが「評価制度」です。評価制度は、単なる業績評価に留まらず、公正な処遇の実現や人材育成、組織全体の効率向上など、さまざまな目的を持っています。
本記事では、評価制度の基本的な仕組みやその導入目的、さらには企業が直面する課題への具体的な対応策を詳しく解説します。従業員と組織の双方が利益を受けるために、評価制度の適切な設計と運用がいかに大切であるかを理解しましょう。
目次
評価制度とは

評価制度とは、企業が従業員の業績や能力を適切に評価し、その結果をもとに処遇や育成計画を行う仕組みです。この制度は、従業員一人ひとりの努力や成果を正確に把握し、公平で透明性のある評価を実現することを目的としています。単なる昇給や昇進の基準にとどまらず、従業員の成長を支援する仕組みでもあります。
適切な評価基準を設けることで、従業員は自身の課題や強みを明確にし、スキルアップの意欲を高めることが可能です。さらに、企業にとっても人材の能力を最大限に引き出し、競争力の強化につなげることができます。
評価制度を効果的に運用するためには、基準の明確化と透明性の確保が欠かせません。従業員全員が納得感を持って制度に取り組むことで、組織全体の成長と目標達成が実現されます。
評価制度のトレンド
近年の評価制度は、従来の年次評価や一律のレーティング制度から大きく変化しています。特に注目されているのが「レーティング廃止」の流れで、相対評価による順位付けをやめ、個人の成長や役割への貢献度を重視する企業が増えています。これにより、評価のための競争や不公平感を減らし、社員の主体性や挑戦意欲を高める狙いがあります。
また、目標管理においてもOKRや1on1ミーティングを活用し、短いサイクルでフィードバックを行う仕組みが主流になりつつあります。評価を「査定」ではなく「成長支援」と捉える考え方が広がっており、柔軟で納得感のある制度設計が、これからの人材定着や組織力強化の鍵となっています。
関連記事:評価制度の意義とは?目的、メリット・デメリットを徹底解説
人事評価制度とは?導入目的について
人事評価制度は、従業員の働きやスキル、成果を正確に測定し、その評価結果をもとに処遇や育成計画を決定する仕組みです。この制度の導入目的は、主に以下の3つに分類されます。それぞれが組織運営で大事な役割を果たし、従業員と企業双方にとって有益な効果をもたらします。
処遇の決定
人事評価制度の中心的な目的は、従業員の処遇を公平かつ適切に決定することです。評価結果に基づいて昇給や昇進、ボーナスなどの基準を明確化することで、従業員が自身の努力や成果が正当に評価されていると実感できるようになります。このような公平性のある処遇決定は、従業員のモチベーション向上に直結します。
さらに、評価基準を透明性のある形で運用することが大切です。不公平感や不信感が組織内に広がると、職場環境に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、評価プロセスを明確にし、従業員が納得できる仕組みを構築することが必要です。こうした取り組みは、組織全体の信頼関係を強化する基盤となります。
最適な人材配置
評価制度は、従業員のスキルや適性を正確に把握し、適材適所の配置を実現するための欠かせないツールです。この制度を活用することで、リーダーシップを発揮できる人材を管理職に配置し、専門知識やスキルが求められる役割には適切な従業員を配置するなど、組織全体の効率性を向上させることができます。
また、組織内のリソースを最適化することで、生産性が向上し、長期的な成長基盤を構築することが可能です。このようなプロセスを通じて、個人の能力を活かしながら、企業全体の競争力を高めることができます。適材適所の実現は、従業員と企業双方にメリットをもたらす戦略的な施策です。
人材育成による業績向上
評価制度は、従業員の成長を支援する効果的な仕組みです。評価結果を活用して、従業員の悩みの課題や強みを明確にし、それに基づいた研修やスキルアッププログラムを提供することで、成長を加速させることができます。このプロセスにより、従業員の能力が引き出すだけでなく、キャリア目標をより具体的に描けるようになります。
従業員が自己成長を実感できる環境を整えることで、職場への定着率が向上し、結果として優秀な人材を維持することができるでしょう。さらに、従業員が高い努力を持って働くことで、企業全体の生産性や業績向上に直結します。 人材育成に力を入れることは、長期的な企業競争力の確立に欠かせない要素です。
関連記事:人事評価制度の目標設定完全ガイド:書き方、例文、SMART、面談のコツを徹底解説
関連記事:人事評価制度の目的とは?メリット・デメリットや種類を紹介
人事評価制度の種類
人事評価制度にはさまざまな種類があり、企業の目的や文化組織に応じて適切な方法が選択されます。それぞれの評価制度は特徴が異なり、従業員の成長促進や業績向上に役立ちます。
MBO(目標管理制度)
MBO(Management by Objectives)は、従業員と企業が事前に解決した目標に基づいて評価を行う方法です。個人の目標が組織全体の目標に紐づくため、全体的な会社の方向性に沿ったパフォーマンスの向上が期待されます。
この評価制度の特徴は、目標が明確であるため従業員のモチベーションが判断しやすい点です。また、成果が具体的に数値化されることで、評価の透明性が向上します。設定を考えると本来の目的を達成できない可能性があるため、適切な目標設計が必要です。
| メリット | ・目標が明確なため、評価基準が分かりやすい ・成果が数値化しやすい ・営業職など成果が可視化しやすい職種では、モチベーション向上につながりやすい |
| デメリット | ・短期的な成果に偏りやすい ・目標設定が不適切だと、本来の業務価値を正しく評価できない |
| 具体例 | 営業部門で売上目標を設定し、その達成率を評価に反映するケース |
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、従業員が職務を遂行する上で求められる能力や行動特性を基礎に評価する方法です。この認定では、スキルや知識だけでなく、リーダーシップや問題解決能力など行動面を評価する対象となります。
この評価は、従業員の能力開発に重点を置き、組織全体のスキルレベルを底上げできる点です。 特に中長期的な視点での人材育成を重視する企業に適しています。設計が解消すると評価の一貫性が考慮される可能性があるため、基準設定に注意が必要です。
| メリット | ・人材育成と評価を連動させやすい ・中長期的な視点で組織のスキルレベルを底上げできる ・成果がすぐに見えにくい職種でも、公平な評価が可能 |
| デメリット | 評価基準が曖昧だと、評価者によるばらつきが生じやすい |
| 具体例 | 管理職候補に対して「部下育成力」「判断力」などの行動指標を設定し、昇進評価に活用するケース |
360評価
360度評価は、上司、同僚、部下、顧客など複数の評価者が従業員を多角的に評価する方法です。多様な視点からフィードバックを得る課題で、個人の強みを明確に確立し、公平性や透明性が向上します。
従業員は自己を中心に、具体的な成長の指針を得ることができ、組織全体の意識向上やコミュニケーション活性化にも対応します。適切な基準設定と運用が求められるこの制度は、個人と組織の成長を支える効果的な手法です。
| メリット | ・評価の公平性、透明性が高まる ・本人が気づいていない強みや課題を把握できる ・組織全体のコミュニケーション活性化にもつながる |
| デメリット | ・評価者の主観や人間関係の影響を受けやすい ・運用設計を誤ると不満につながる可能性がある |
| 具体例 | 管理職に対してリーダーシップやマネジメント力を多面的に評価し、育成目的で活用するケース |
関連記事:人事評価制度で見る優良企業8選!働き方改革の最前線
評価基準として有効な評価項目

効果的な人事評価制度を構築するためには、適切な評価項目を設定することが不可欠です。この評価項目が従業員の努力や成果を正確に把握し、公平な評価を行う基盤となります。これらの項目をバランス良く取り入れることで、組織全体のパフォーマンス向上に繋がる評価制度を実現できます。
能力
能力を評価基準として設定することは、効果的な人事評価制度を構築する上で欠かせません。能力とは、従業員が業務を遂行するために必要なスキルや知識、そしてその活用方法を指します。具体的には、業務に関する専門知識を深く理解し、実務に適用できているか、課題に対する問題解決力が十分であるかなどが評価のポイントとなります。
また、顧客や同僚と良好な関係を築くためのコミュニケーション能力も、仕事を円滑に進める上で大切な要素です。能力評価を通じて、従業員の長所や改善点を明確にし、彼らがより高いパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが可能となります。
プロセス
業務の結果だけに注目するのではなく、その過程を評価するプロセス基準も、とても大切な評価要素です。従業員が業務に取り組む際にどれだけ計画的であるか、目標を達成するためにどのような努力を重ねているか、チームメンバーと協力しながらプロジェクトを進めているかなどが評価されます。
ちなみに弊社が評価制度を設計する際には、評価要素に「会社の理念に沿った行動ができているか」を取り入れています。こうすることで、会社の理念が自然と社員に浸透し、結果として社員のモチベーション向上や会社の成長に繋がることが期待できます。経営理念がもたらす会社への驚きの効果については、ぜひ下記の関連記事をご覧ください。
関連記事:企業理念と経営理念の違いとは?策定•浸透方法も徹底解説
また、現状に甘んじることなく、常に改善を目指す姿勢があるかも評価の大切なポイントです。プロセス評価は、結果では測りきれない努力や工夫を認め、従業員のモチベーションを高めることにつながります。
成果
成果は、従業員がどれだけ組織の目標達成に貢献したかを測る最も明確な指標です。売上や利益率、プロジェクトの成功率などの数値目標の達成度が評価されるほか、顧客からの満足度や信頼を得られているかどうかも大切な観点となります。
さらに、自分自身やチームの業務を効率化し、それが全体の成果につながった場合、その取り組みも評価に含まれます。こうした成果評価を取り入れることで、従業員は達成感を得るだけでなく、次なる目標への意欲を高めることができるでしょう。
評価軸として押さえるべき3つの視点
人事評価制度を設計するうえでは、評価項目を「業績評価」「能力評価」「情意評価」という3つの評価軸で整理することが欠かせません。これらはそれぞれ異なる役割を持っており、いずれか一つに偏ると評価の公平性や納得感が損なわれる恐れがあります。3軸をバランスよく組み合わせることで、成果と行動、姿勢の両面から従業員を正しく評価できます。
業績評価
業績評価は、売上高や利益、目標達成率など、数値で把握しやすい成果を評価する軸です。成果が可視化されやすいため評価の透明性が高く、営業職やプロジェクト型業務などでは特に有効です。一方で、短期的な成果に偏りやすい側面があるため、他の評価軸と併用することが重要です。
能力評価
能力評価は、業務遂行に必要な知識やスキル、問題解決力、行動特性などを評価する軸で、将来の成果につながる要素を見極める役割を担います。成果がすぐに表れにくい職種や若手社員の評価にも適しており、人材育成や配置判断の基準として活用できます。
情意評価
情意評価は、勤務態度や責任感、協調性、主体性といった仕事への向き合い方や姿勢を評価する軸です。数値化しにくい要素ではありますが、組織風土の醸成やチームワークの向上に大きく影響します。
人事評価制度を設置するまでの流れ

まず、人事評価制度の目的を明確に設定することが最初のステップです。評価の目標が不明瞭だと、従業員に評価制度の意義が伝わらず、制度自体が形骸化するリスクがあります。
例えば、スキル向上を支援するのか、成果に応じた公正な報酬を提供するのか、または組織全体の効率を改善するのかを具体的に定めます。目標を明確にすることで、評価基準やプロセスが統一され、従業員の理解と納得を得やすくなるでしょう。
人事評価の目標設定
人事評価制度を導入する最初のステップは、評価の目標を明確にすることです。この段階では、制度を通じて何を達成したいのかを具体的に定める必要があります。例えば、従業員のスキル向上を促進したいのか、成果に応じた公正な報酬体系を構築したいのか、あるいは組織全体の効率を向上させたいのか、目標を明確にすることで、評価制度の基盤が確立されます。
目標を設定する際には、企業のビジョンや長期的な目標と整合性を持たせることが必要です。また、従業員の理解を深めるため、目標が具体的で測定可能な形に落とし込まれていることが求められます。このように目標を明確化することで、評価基準やプロセスが統一され、制度全体がスムーズに機能しやすくなるでしょう。
評価項目の設定
次に進むべきステップは、評価項目の設定です。評価項目は、従業員が日々の業務で目指すべき基準や方向性を具体化する指針となります。例えば、能力評価では業務遂行に必要な専門スキルや問題解決能力が焦点となり、プロセス評価では業務遂行の計画性や協調性、成果評価では具体的な業績や目標達成度が評価の中心です。
また、評価項目は公平性と透明性を確保するために、具体的かつ明確に設定されるべきです。曖昧な基準は主観的な評価を助長し、信頼性を損なう原因となるため注意が必要です。従業員が自分の評価基準を十分に理解できるよう、事前に丁寧な説明を行うことも望まれます。このステップを確実に進めることで、評価制度の信頼性が大きく向上するでしょう。
さらに、厚生労働省では仕事に必要なスキルや知識を業種別に整理した「職業能力評価基準」の展開もしています。インターネットで公開している公的基準となるので、幅広い分野で活用できます。
反映方法の査定
評価結果をどのように従業員の待遇や成長に反映させるかを設計することも、制度の効果を引き出すために大切です。評価結果は昇給や昇進、ボーナス支給の基準となるだけでなく、従業員のキャリア形成やスキルアップにも影響を与えます。そのため、評価結果がどのような形で待遇に反映されるのかを具体的に定め、従業員に説明することが必要不可欠です。
また、評価結果をもとに適切なフィードバックを行うことで、従業員は自分の強みや課題を理解し、次の目標に向けて努力する動機づけが得られます。これにより、従業員が評価制度を信頼し、自分の成長に結びつけられる仕組みを作ることができます。
従業員への周知
最後のステップは、評価制度を従業員に周知することです。どれほど優れた制度であっても、従業員に正確に理解されなければ、実効性を失う恐れがあります。周知には、全社ミーティングや説明会の開催、マニュアルやガイドラインの配布の手法が効果的です。
さらに、従業員が制度の詳細に関する疑問を解消できる場を設けることで、制度に対する納得感を高めることができます。
周知活動では、評価制度の目的や仕組みが明確に伝わるよう、平易な言葉で説明することが求められます。従業員が制度を十分に理解し、納得した上で参加できるような体制を整えることで、制度の効果を最大化することが可能となるでしょう。
評価制度を導入し成功した事例3選
株式会社メルカリ
フリマアプリで知られる株式会社メルカリは、「OKR」と「バリュー評価」の2軸による人事評価制度を採用し、四半期ごとに評価を行っています。OKRは2015年に導入され、達成度そのものではなく、目標に向かうプロセスや発揮された成果・行動を重視する点が特徴です。
一方、バリュー評価では、同社が掲げる3つの行動指針をどれだけ実践できているかを評価します。評価の参考としてピアボーナス制度を活用し、感謝や称賛の可視化を促進するとともに、受賞者や貢献度の高い社員を表彰する仕組みを整えています。
GMOインターネット株式会社
インターネット関連事業を展開するGMOインターネット株式会社では、人事評価制度に360度評価を導入しています。評価は6段階の等級とランクによって構成され、目標の達成度に応じて給与が決定される仕組みです。
この制度の根底には、経営のあらゆる側面を可視化するという同社のポリシーがあります。全スタッフの等級やランクが社内で公開されており、各等級に対応する給与水準もオープンにすることで、評価や処遇に対する高い透明性と納得感を実現しています。
株式会社ディー・エヌ・エー
モバイルゲーム開発やSNS運営、電子商取引サービスを展開する株式会社ディー・エヌ・エーでは、半期ごとに人事評価を実施しています。評価は「成果(業績)」と「発揮能力(成長度合い)」の2軸で構成され、成果はボーナス、発揮能力は基本給にそれぞれ反映される点が特徴です。
能力については、半年ごとに上司と目標を設定し、その達成度をもとに評価を行い、グレード階層と照らし合わせて給与が決定されます。さらに、約130名のマネージャーを対象に実名での360度評価を導入しており、評価ではなくフィードバックを目的とすることで、マネージャーとメンバー間の信頼関係構築に活用しています。
参照:DeNAの人事制度に学べ!(前編)基本給は「成果」ではなく「成長」で決まる!?
評価制度のご相談は「マイビジョン」へ
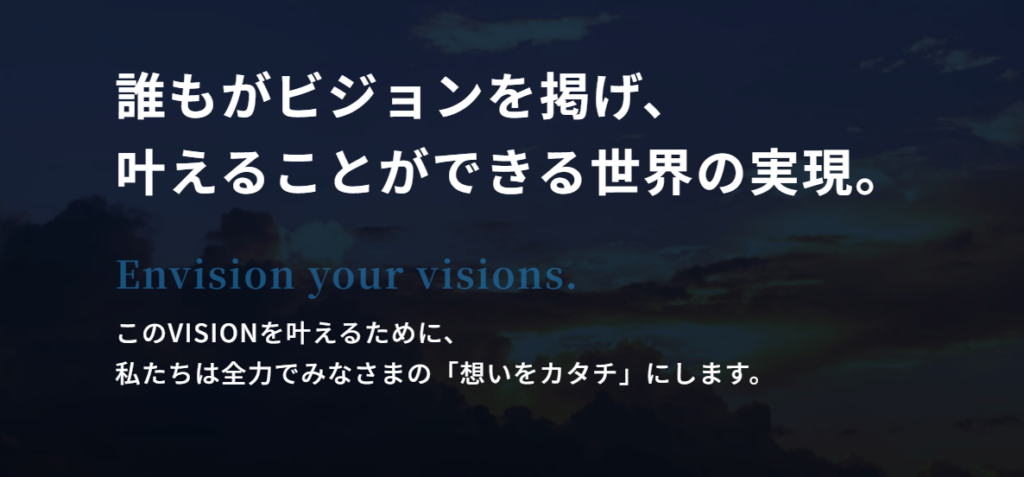
株式会社マイビジョンは、企業理念の策定・浸透支援を軸に、人事評価制度設計や採用戦略構築までを一気通貫で支援するコンサルティング会社です。経営者の想いやビジョンを言語化し、それを評価制度や人材育成の仕組みに落とし込むことで、「理念が現場で機能する組織づくり」を実現している点が大きな特徴です。
特に中小企業において課題となりやすい、評価の属人化や社員の納得感不足に対し、成長と成果の両立を意識した制度設計を強みとしています。評価制度の見直しや新設を検討している場合は、理念と制度をつなぐ設計に強いマイビジョンへの相談がおすすめです。
まとめ
評価制度とは、企業が従業員の業績や能力を正確に評価し、その結果をもとに処遇や育成計画を決定する仕組みです。この制度は、公平な処遇の実現、最適な人材配置、そして従業員の成長を支援することを目的としています。評価結果に基づき昇給や昇進を決定するだけでなく、従業員の強みを引き出し、課題解決を促進する研修やスキルアップの機会を提供します。
マイビジョンでは、ミッション・ビジョン・バリューの明確化から、中期ビジョンや判断軸の設定までを一貫してサポートします。ブランドが描く未来を具体的な成果へとつなげるためのパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。