インナーブランディングの成功事例10選!具体例からわかる成功のポイントも紹介

企業のブランド力を高め、従業員のエンゲージメントを向上させる「インナーブランディング」。
近年、多くの企業がこの手法を取り入れ、成功事例も増えています。
しかし、どのように実践すれば効果的なのか、具体的な手法が分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、企業の成功事例をもとに、インナーブランディングの重要性や成功のポイントを解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
インナーブランディングとは?成功事例から学ぶ重要性
企業の成長には、社外向けのブランディングだけでなく、社内の価値観を統一する「インナーブランディング」も欠かせません。
実際に成功事例を持つ企業は、どのような施策を行っているのでしょうか?
具体的な取り組みを通じて、その重要性を解説します。
インナーブランディングの目的
インナーブランディングは、単なる社内広報ではなく、企業の価値観やビジョンを従業員に浸透させ、意識を統一するための施策です。
社員が企業の理念を理解し、共感することで、組織の一体感が強まり、業務への主体性やモチベーションが底上げされます。
また、企業文化を深く理解した従業員が増えると、顧客対応の質が改善し、ブランドの信頼性が高まるというメリットもあります。
顧客との接点を持つ社員が企業の価値観を自然に体現できれば、ブランドの印象をより強くすることができるでしょう。
さらに、社内に一貫した価値観が根付けば、従業員の定着率アップにもつながり、採用活動においても自社に合った人材を引き寄せやすくなります。
通常のブランディングとの違い
ブランディングには、大きく分けて「アウターブランディング」と「インナーブランディング」の二つがあります。
ブランディングといえば、顧客や市場に向けたアウターブランディングが一般的ですが、これは、広告やPR活動を通じてブランドの認知度や価値を高める手法です。
一方、インナーブランディングは、社内の従業員に対してブランドの価値を浸透させること。
企業理念やビジョンを共有し、組織の一体感を高めて、社員のエンゲージメントを強化します。
外向けのブランディングが企業のイメージを形作るのに対し、インナーブランディングは「ブランドを支える人材の育成」にフォーカスしている点が大きな違いです。
関連記事:インナーブランディングとは? 目的、メリット、成功事例を徹底解説
インナーブランディングの成功事例10選
インナーブランディングに成功した企業の共通点は、独自の施策を通じて組織の結束力を高め、企業価値を進化させている点です。
ここでは、5社の事例を取り上げ、それぞれの取り組みを紹介します。
成功のポイントを学び、自社に活かせる施策を見つけていきましょう。
【事例①】日本航空株式会社
日本航空(JAL)は、経営破綻を乗り越え、インナーブランディングを活用して企業文化を再構築しました。
組織再生の鍵となったのは、従業員の意識改革です。
JALでは幹部の意識改革から始め、従業員全員が共通の価値観を持てるよう、「JALフィロソフィ」を作成し、社内に浸透させました。
具体的には、幹部向けの勉強会を週4回開催し、社員同士のつながりを深める機会を設けることで、組織の一体感を高めました。
結果として、従業員の主体性が向上し、企業全体の価値観が統一され、再建を成功に導きました。
参考:JAL再建の奇跡”はなぜ実現できたのか|TKCグループ
【事例②】スターバックスコーヒージャパン
スターバックスコーヒージャパンは、インナーブランディングを通じて従業員の意識統一と企業文化の強化に成功しています。
ブランドの基盤となるのは、「人」「コミュニティ」「地球」の3つの価値観を大切にする姿勢です。
具体的には、多様性を尊重し、すべての従業員が自分らしく働ける環境を整えるとともに、地域社会とのつながりを深める活動を展開しています。
その結果、従業員の企業への愛着が高まり、ブランドの価値を体現する文化が社内外に広がっています。
参考:10年ビジョン|スターバックスコーヒー
【事例③】株式会社リクルート
株式会社リクルートは、インナーブランディングの強化を通じて、従業員の主体性を引き出し、働きがいのある職場づくりを推進しています。
多様な価値観を尊重し、個人と組織がフラットな関係を築くことに注力しています。
その一環として、社内の優れた取り組みを表彰する「GOOD ACTION AWARD」を実施し、職場環境の改善を促しています。
こうした施策により、従業員のエンゲージメントが高まり、企業文化の定着と成長につながっています。
参考:イキイキと働ける職場づくりの取り組みに光を当てる|株式会社リクルート
【事例④】東京ディズニーリゾート
東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、「TheFiveKeys~5つの鍵~」を基に、従業員の意識統一を図るインナーブランディングを推進しています。
この指針は、Safety(安全)、Courtesy(礼儀正しさ)、Inclusion(インクルージョン)、Show(ショー)、Efficiency(効率)の5つから成り、特に「Show(ショー)」の概念が特徴的です。
キャストはパーク全体を舞台と捉え、自身がショーの一部であるという意識を持つよう教育しています。
また、「Courtesy(礼儀正しさ)」では、すべてのゲストをVIPとして扱うことを徹底。
新人研修を通じて相手の気持ちを考えたおもてなしを学び、日々の業務で実践することで、キャスト一人ひとりが企業理念を深く理解し、ディズニーならではの特別な体験ができる組織風土を築いています。
参考:パーク運営の基本理念|OLC GROUP
【事例⑤】ヤンマー
ヤンマーは、企業の価値観を従業員に浸透させるため、インナーブランディングに力を入れています。
その中心にあるのが、「HANASAKA」という理念で、個々の挑戦を後押しし、自発的な行動を促すことを重視しています。
具体的には、国内外で「HANASAKAワークショップ」を実施し、社員が主体的にブランドを考え、共有できる場を設けています。
この取り組みにより、組織の一体感が生まれ、企業のブランド価値がさらに強化されています。
参考:“ヤンマーらしさ”について社員が改めて考える 「人」が起点のブランディングと“HANASAKA”の関係とは?|YANMAR
【事例⑥】株式会社マクロミル
マクロミルは、社員一人ひとりが企業理念や事業の意義を理解し、自律的に行動できる組織づくりを重視しています。
インナーブランディング施策として、理念やバリューを軸にした評価制度や1on1ミーティングを導入し、日常業務と理念を結びつける仕組みを構築しました。
また、社員同士が価値観を共有する対話の場を継続的に設けることで、組織内の共通言語を形成しています。
結果として、社員のエンゲージメント向上と意思決定スピードの改善につながっています。
【事例⑦】USJ
USJは「ゲストに最高の体験を提供する」という理念を軸に、徹底したインナーブランディングを行っています。
アルバイトを含む全スタッフに対し、理念や行動指針を体験型研修や日常のコミュニケーションを通じて浸透させている点が特徴です。
役職や雇用形態に関係なく、全員が“ブランドの担い手”であるという意識を持つことで、現場の判断力やサービス品質が向上し、USJならではの一体感ある組織文化を築いています。
【事例⑧】株式会社サカイ引越センター
サカイ引越センターは、「まごころこめておつきあい」という理念をインナーブランディングの中核に据え、社員一人ひとりの行動とブランド価値を強く結びつけています。
引越しサービスは現場対応が品質を左右するため、研修や評価制度に理念を明確に反映し、行動基準を全社で統一してきました。
さらに、エリアごとに「ブロック広報員」を配置することで、本部のメッセージや取り組みを各支社へ確実に浸透させる体制を構築。
約20年ぶりのユニフォーム刷新時には記者発表会を行い、その背景や意義を社員に共有することで、自社ブランドへの誇りと当事者意識を高めることに成功しています。
【事例⑨】株式会社ジェイテクト
ジェイテクトは、製造業としての高い技術力に加え、「人」を軸とした企業文化づくりをインナーブランディングの重要テーマとしています。
各事業部の希望に応じて製品や配信時期を整理し、計画的にプレスリリースを立案することで、現場と広報が連動する体制を構築しました。
迅速に動ける仕組みを整え、関係部署との信頼関係や情報共有を強化しています。
また、受賞社員を称える場を設け、インタビューを通じて取り組みや想いを社内に発信することで、社員の当事者意識とモチベーション向上につなげています。
こうした施策が、理念の浸透と組織の一体感、継続的な改善文化の定着を支えています。
【事例⑩】株式会社マネーフォワード
マネーフォワードは、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを軸に、インナーブランディングと情報発信を一体化させた取り組みを進めています。
ミッションやバリューを採用・評価・日常の意思決定にまで一貫して反映させるだけでなく、統合報告書や人事制度そのものを「自社の姿勢を表す情報」として積極的に発信している点が特徴です。
発信先はメディアに限定せず、社員や求職者、取引先など多様なステークホルダーにそのまま届くことを意識し、「ワクワク」「未来志向」といった自社のマインドを表現に反映しました。
さらに、産休・育休ガイドブックの配信を通じて従業員による自発的な情報共有が広がり、男性育休取得率は約9割に到達しました。
こうした取り組みが、カルチャーの浸透と高いエンゲージメントの維持につながっています。
関連記事:リブランディングとは?意味・目的・成功事例を徹底解説!
関連記事:ブランディングの成功事例10選|目的やマーケティングとの違いについても詳しく解説!
インナーブランディングのメリット
インナーブランディングを強化すると、従業員のエンゲージメントが高まり、企業価値が向上します。
ここからは、インナーブランディングの具体的なメリットを見ていきましょう。
従業員の定着率の向上
インナーブランディングを強化すると、従業員が企業の理念やビジョンに共感し、働く意義を実感できるようになります。
その結果、組織への帰属意識が高まり、定着率改善にもつながるでしょう。
企業の価値観が不明確な職場では、従業員は自分の仕事に対する意義を見いだせず、離職率が高くなりがちです。
一方、明確な理念があり、それを日常業務の中で意識できる環境が整っている企業では、従業員が主体的に働きやすくなります。
企業価値の向上
インナーブランディングの強化は、企業理念が従業員に浸透し、ブランドの一貫性が確保されるため、企業価値の向上につながります。
つまり、企業価値を高めるためには、インナーブランディングを通じて、理念と実践のギャップを埋めるということです。
従業員が企業のミッションを深く理解し、日々の業務で実践できる環境が整うと、顧客対応の質が向上し、サービス全体のクオリティが安定します。
たとえば、理念を体現する従業員が増えれば、どの店舗・部署でも一貫したブランド体験を提案できるようになり、顧客の信頼獲得につながるでしょう。
また、ブランド価値が高まれば、競争優位性が強化され、長期的な企業成長を支える要素となります。
従業員が誇りを持てる環境を築くことで、企業文化がより魅力的になり、採用市場でも優秀な人材を引きつけることができるでしょう。
従業員のエンゲージメント向上
インナーブランディングを推進することで、従業員の会社に対する共感や愛着が高まり、エンゲージメントが向上します。
その結果、自分の仕事が会社に貢献していると実感しやすくなります。
例えば、経営層と従業員が定期的に対話できる機会を設けると、会社のビジョンが身近なものになります。
トップの考えを直接聞けることで、自分の役割を再認識し、日々の業務へのモチベーションへとつながります。
成功事例からわかるインナーブランディングを成功させるためのポイント
成功企業の事例を見ると、インナーブランディングの効果を最大化するための共通点が見えてきます。
単に理念を掲げるだけではなく、従業員が共感し、自発的に行動できる仕組みを整えましょう。
ここでは、具体的なポイントを解説し、自社に活かせる方法を探っていきます。
目的を明確化する
インナーブランディングを成功させるには、なぜ実施するのか、その目的を明確にしましょう。
企業理念の共有、従業員のエンゲージメント向上、組織文化の強化など、目指すゴールをはっきりさせることで、施策の方向性が定まります。
目的が曖昧なままだと、従業員にとって理念が単なるスローガンになり、実践につながりません。
例えば、従業員が企業理念を理解し、業務に活かすことを目的とするなら、日常業務と結びついた研修やミーティングを設けましょう。
また、目標を定期的に確認し、従業員の意見を取り入れて、組織全体が共通のゴールを持つようにします。
目的を明確にし、実践につなげる仕組みを整えることが、インナーブランディング成功への一歩です。
定期的に効果を測定する
インナーブランディングを成功させるためにも、施策が従業員にどの程度浸透し、実際に成果を上げているかを把握することも大切です。
定期的に効果を測定し、必要に応じて改善を行いましょう。
例えば、従業員アンケートを実施し、理念の理解度や共感度を定量的に測る方法があります。
フィードバックを集めることで、どの施策が効果的だったのかが明確になり、改善点も見えてきます。
また、離職率や従業員満足度の推移を確認し、インナーブランディングの影響を分析しましょう。
定期的なチェックを行い、企業文化がどのように変化しているのかを可視化することが、組織の成長につながります。
自社に合う手法やツールを使用する
インナーブランディングの成功には、自社の文化や従業員の特性に合った手法やツールを選びましょう。
企業によって働き方や価値観は異なるため、画一的なアプローチでは十分な効果を得られません。
大切なのは、自社の特徴に合わせた手法を取り入れ、従業員が共感しやすい形で理念を浸透させることです。
例えば、リモートワークを導入している企業では、オンラインでの理念共有が重要です。
社内ポータルや動画配信ツールを活用し、経営層からのメッセージを定期的に発信することで、従業員との距離が縮まり、一体感が生まれます。
また、対面コミュニケーションが重視される企業では、ワークショップや研修を活用し、理念を実際の業務と結びつける機会を増やします。
成功事例の共有やディスカッションを通じて、従業員が主体的にブランドを体現できる環境を作りましょう。
関連記事:ブランディングの成功事例10選|目的やマーケティングとの違いについても詳しく解説!
インナーブランディングを成功させるためのステップ
インナーブランディングを成果につなげるためには、思いつきの施策を実行するのではなく、「計画・実行・評価・改善」という一連の流れを意識することが重要です。
ここでは、各ステップで押さえるべきポイントと具体的な手法を解説します。
ステップ1:計画(目的と軸の明確化)
まずは、インナーブランディングを通じて「何を実現したいのか」を明確にします。
理念浸透、エンゲージメント向上、行動変容など目的を定め、その軸となるミッション・ビジョン・バリューやステートメントを整理します。
この段階では、社員アンケートや1on1、ワークショップなどを活用し、現状の課題や価値観のズレを把握することが効果的です。
ステップ2:実行(施策の設計と展開)
次に、目的に沿った具体施策を設計・実行します。
代表的な手法としては、社内イベント、研修、評価制度への反映、社内報や動画配信などがあります。
重要なのは、一過性で終わらせず、日常業務や制度と結びつけることです。
社内SNSやイントラネットなどのツールを活用し、継続的に情報を届ける仕組みを整えましょう。
ステップ3:評価(効果測定と可視化)
施策を実施した後は、効果を定期的に評価します。
エンゲージメントスコア、離職率、社員アンケートの変化、行動事例の増加など、定量・定性の両面で確認することが重要です。
数値だけでなく、「どのような行動が増えたか」を可視化することで、施策の手応えを組織全体で共有できます。
ステップ4:改善(継続的なアップデート)
評価結果をもとに施策を見直し、改善を重ねていくことがインナーブランディング成功の鍵です。
社員の声を反映しながら内容や伝え方を調整し、組織の成長フェーズに合わせてアップデートしていきます。
このサイクルを回し続けることで、理念やブランドは「浸透するもの」から「行動として根付くもの」へと進化していきます。
社内コミュニケーションを活性化させるための施策
インナーブランディングを機能させるうえで、社内コミュニケーションの活性化は欠かせません。
理念や価値観は、一方的に伝えるだけでは浸透せず、日常的な対話や共有を通じて初めて行動に結びつきます。
ここでは代表的な施策と、その特徴、導入時のポイントを解説します。
社内報・社内メディア
社内報は、理念や方針、社員の取り組みを継続的に伝えられる施策です。
成功事例では、経営メッセージだけでなく、現場社員のストーリーや成功体験を掲載することで共感を生んでいます。
一方、失敗例として多いのは「読むだけで終わる」状態です。
一方通行にならないよう、コメント機能や連動企画を設けることが重要です。
社内SNS
社内SNSは、部署や役職を超えた情報共有や雑談を促進できる点がメリットです。
スピード感のあるコミュニケーションが生まれ、組織の一体感向上につながります。
ただし、目的が曖昧だと投稿が定着せず形骸化しがちです。
運用ルールや投稿テーマを明確にすることが成功の鍵となります。
ワークショップ
ワークショップは、社員同士が対話を通じて価値観を共有できる施策です。
理念理解や行動変容を促しやすい一方、準備不足だと「やらされ感」が強くなるリスクがあります。
テーマ設定やファシリテーションの質が成果を左右します。
社内イベント
表彰式や交流イベントは、感謝や称賛を可視化し、モチベーション向上につながります。
成功事例では、理念や行動指針と紐づけて設計されています。
単なるレクリエーションに終わらせないことがポイントです。
定期的に効果を測定する
インナーブランディングを成功させるためには、施策を実行して終わりではなく、定期的に効果を測定し改善につなげることが重要です。
代表的な方法として、従業員アンケートは理念理解度や共感度、社内コミュニケーションの満足度を把握するのに有効です。
加えて、360度評価を活用することで、価値観や行動指針が実際の行動に反映されているかを多面的に確認できます。
さらに、eNPS(Employee Net Promoter Score)は「自社を他人に勧めたいか」という質問を通じて、エンゲージメントや愛着度を数値化できる指標です。
これらの結果を単発で見るのではなく、時系列で比較し課題を特定したうえで、施策の見直しや新たな改善策を立案することで、インナーブランディングのPDCAサイクルを効果的に回すことが可能になります。
インナーブランディングを成功させるための注意点
インナーブランディングは、従業員の共感と行動を引き出すことがポイントです。
しかし、進め方を誤ると、形骸化し、期待する効果を得られません。
ここでは、実践する際に注意すべきポイントを解説します。
従業員に価値観を押し付けない
インナーブランディングを進める際に大切なのは、企業の理念を従業員に強制しないことです。
価値観の押し付けは、かえって反発を生み、浸透を妨げる原因になることも。
従業員一人ひとりが企業理念を自分の言葉で解釈し、納得感を持って行動できなくてはインナーブランディングの意味がありません。
例えば、トップダウンでの一方的な発信ではなく、ワークショップやディスカッションの場を設け、従業員が主体的に考える機会を作るようにします。
中長期的な視点を持つ
インナーブランディングは、一度の施策で完了するものではなく、企業文化として根付かせるには時間がかかるものです。
短期間で結果を求めるのではなく、長期的な視点を持ち、継続的に取り組みましょう。
例えば、社内研修や理念共有の場を単発で終わらせるのではなく、定期的なフォローアップや従業員の意見を反映した改善を行うことで、組織全体に定着しやすくなります。
また、経営層が積極的に関わり、理念を自ら体現することで、社員の理解度も深まります。
さらに、企業の成長や市場環境の変化に応じて、インナーブランディングの内容も進化させましょう。
従業員が理念を自分ごととして捉え、長く働きたいと思える環境を作ることが、企業の持続的な発展につながるのです。
経営理念に沿って取り組む
インナーブランディングは、企業の経営理念と一貫性を持たせましょう。
理念とずれた施策を実施すると、従業員の共感を得られず、形骸化してしまうかもしれません。
例えば、企業が「挑戦」を重視する理念を掲げているなら、新しいアイデアを発信しやすい環境を整えます。
評価制度にも反映させることで、従業員が理念を意識しながら行動できるようになります。
また、経営層が理念を体現し、率先して実践しましょう。
トップが理念を日々の業務で実践することで、従業員にも自然と浸透していきます。
さらに、社内のコミュニケーションを強化し、理念を共有する機会を増やすことで、組織全体の一体感も高まります。
関連記事:経営理念浸透のメカニズムとは?具体的な方法を徹底解説!
インナーブランディングについてのご相談は「マイビジョン」へ
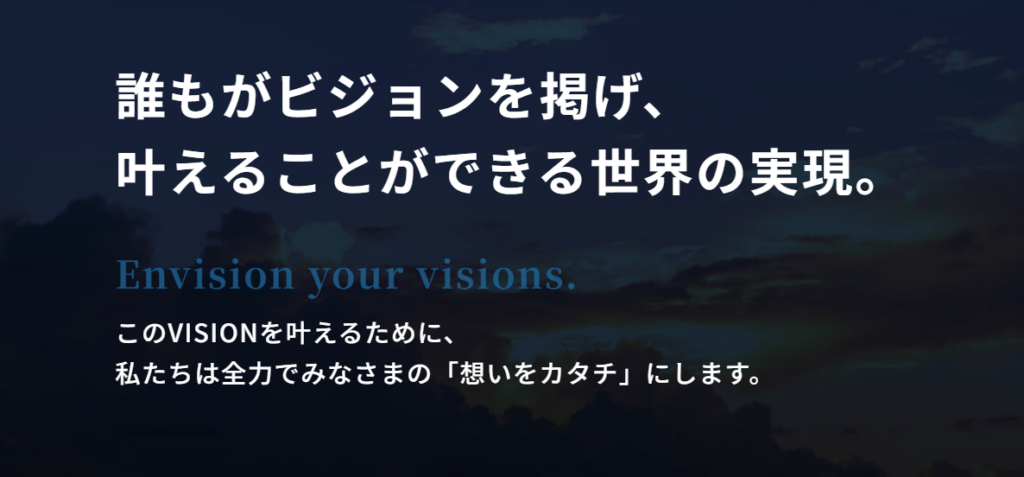
インナーブランディングの進め方に悩んでいる方や、理念が社内に浸透していないと感じている方は、「マイビジョン」へご相談ください。
企業の想いや価値観を丁寧に言語化し、評価制度や社内コミュニケーションと連動した実践的なインナーブランディングを支援しています。
まとめ
インナーブランディングは、従業員のエンゲージメント向上や企業価値の強化に欠かせません。
成功企業の事例からもわかるように、理念の浸透や継続的な取り組みが大切です。
しかし、自社に適した施策を見極め、効果的に実践するには専門的な知識が必要です。
マイビジョンでは、貴社の課題に合わせた最適なインナーブランディング戦略を提案し、確実な成果へと導きます。
ぜひお気軽にご相談ください。
参考記事:インナーブランディングとは?重要性や具体的な手法について徹底解説!事例も紹介!|ALL WEB CONSULTING





